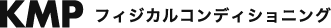高齢化社会が進む中、行政が行う介護予防はますます重要になっています。自治体では健康維持や自立支援のためのプログラムを提供していますが、課題も多く、必ずしも十分な効果を得られているとは限りません。また、その現場に専門職は常駐していません。理由は健康保険・介護保険の利用した病院・施設以外では、医療従事者はその資格を元にした業務ができないからです。言い換えると、医師の指示がなければ業務を行えません。本記事では、行政が行う介護予防の内容や、上記のような問題点を解説し、より効果的な指導を受けるためのポイントを紹介します。介護予防に関心のある方や家族のために、役立つ情報をわかりやすくまとめました。
- 《目次》
- 1. 行政が行う介護予防の内容
- 1-1 介護予防の目的と重要性
- 1-2 行政が提供する主な介護予防サービス
- 2. 行政が行う介護予防の問題点
- 2-1 利用者の認知度が低い
- 2-2 サービスの質や提供体制の課題
- 3. 効果的な介護予防のために必要なこと
- 3-1 科学的根拠に基づいたプログラムの導入
- 3-2 個別対応の強化と継続的なサポート
- 4. 効果のある介護予防の指導を受けるには
- 4-1 介護予防プログラムを積極的に活用する方法
- 4-2 自治体・専門家との連携を深める
- 5. 介護予防の未来と今後の課題
- 5-1 高齢者の意識改革と自主的な取り組みの促進
- 5-2 技術革新を活用した新しい介護予防の可能性
1. 行政が行う介護予防の内容
1-1 介護予防の目的と重要性
介護予防とは、高齢者ができるだけ自立した生活を続けるために、身体機能や認知機能を維持・向上させることを目的とした取り組みです。厚生労働省は、要介護状態になる前に適切な予防策を講じることで、介護費用の抑制と高齢者の生活の質向上を目指しています。
1-2 行政が提供する主な介護予防サービス
自治体では、運動プログラムや健康教室、認知症予防のための講座など、さまざまな介護予防サービスを提供しています。具体的には、地域包括支援センターが中心となり、転倒防止トレーニングや口腔ケア、栄養指導などを実施しています。
2. 行政が行う介護予防の問題点
2-1 利用者の認知度が低い
行政が提供する介護予防プログラムの多くは、十分に周知されていないのが現状です。その結果、サービスが存在しても高齢者やその家族が利用しないケースが多く、十分な効果が発揮されていません。また、認知されるのは要介護認定を受けた高齢者やその家族ばかりで、その予防も「介護度が上がらない事」を目的としていることが多いです。
2-2 サービスの質や提供体制の課題
介護予防サービスの内容は自治体ごとに異なり、質にばらつきがあるのが課題です。また、人手不足や予算の制約により、十分な指導やフォローアップができないケースもあります。認知度の低さでも述べたように、介護認定を受けない心身のケアとなる活動は、病院や介護施設の中で行われています。人材、財源以前の課題があります。
3. 効果的な介護予防のために必要なこと
3-1 科学的根拠に基づいたプログラムの導入
効果的な介護予防を実現するためには、科学的根拠に基づいたプログラムを導入することが不可欠です。運動療法や認知トレーニングなど、医学的に有効とされる方法を積極的に採用することが求められます。それらを発信したり、管理できるのは主に医療従事者ですが、民間で活動する医療従事者の数は本当に少数です。
3-2 個別対応の強化と継続的なサポート
高齢者の健康状態や生活環境は個々に異なるため、個別対応を強化することが重要です。定期的な評価を行い、必要に応じてプログラムを調整することが、効果的な介護予防につながります。しかし、介護保険を利用していない場合、このようなサポートを受けられる事業はほぼありません。予防と言いつつ実際にサポートが開始されるのは介護認定を受けたり、介護が必要な身体機能になってからです。
4. 効果のある介護予防の指導を受けるには
4-1 介護予防プログラムを積極的に活用する方法
まずは、自治体が提供する介護予防プログラムを積極的に利用することが大切です。地域包括支援センターや自治体のホームページで情報を収集し、適したプログラムを見つけましょう。しかし、このような情報収集を高齢者が自立して可能かと言われると、実践し適切なサービスに繋げている高齢者はほとんどいないでしょう。つまり、対象者の家族や周囲の支援者がこうした情報収集に意欲を向けなければ、介護予防は始まりません。
4-2 自治体・専門家との連携を深める
介護予防の効果を高めるためには、自治体や専門家との連携が欠かせません。定期的に専門家のアドバイスを受けることで、より適切な介護予防対策を講じることができます。地域包括支援センター、また民生委員のようなボランティアレベルの地域の支援者により、専門的な他職種の連携のきっかけが生まれます。しかし、対象となる高齢者本人は「大丈夫」と支援を断るパターンは少なくありません。客観的な判断を客観的に受け止められる支援、やはり家族の支えが重要だと考えます。または、事前に地域高齢者に情報を発信し、必要なタイミングが来る前に心構えを促すような活動が有効と考えます。
自治体や専門家の職種を紹介
・民生委員:地域住民の生活や福祉に関する相談に応じ、援助を行う非常勤の地方公務員
・保健師:地域住民の健康増進や生活習慣病対策、母子保健対策などを行う
・社会福祉士:身体や精神に障がいのある人、生活困窮者、高齢者など、日常生活に支障のある人の相談援助を行う
・ケアマネージャー:要介護認定された人が、適切な介護サービスを受けられるようにするために、介護サービス計画(ケアプラン)を作成する
・リハビリセラピスト(PT:理学療法士、OT:作業療法士):医師の指示に基づいてリハビリを行う
5. 介護予防の未来と今後の課題
5-1 高齢者の意識改革と自主的な取り組みの促進
介護予防の成功には、高齢者自身の意識改革が必要です。行政の支援だけでなく、日常生活の中で自主的に健康管理を行う習慣を身につけることが重要です。KMPではこの意識改革に取り組んでいます。他記事で集団リハビリである「KMPスタジオクラス」を紹介しています。提供している内容、事業としての狙い、期待する効果、簡単にですが記事にしているので下記のリンクからぜひ閲覧を。
/スタジオクラス/
5-2 技術革新を活用した新しい介護予防の可能性
今後は、ICTやAI技術を活用した新しい介護予防の形が期待されています。例えば、デジタルデバイスを活用した健康管理アプリやオンライン運動指導など、より効率的な介護予防の実現が可能になるでしょう。現在もバイタルのチェック・記録、運動療法の管理などのヘルスケアに関するアプリなどが多数開発されています。それを扱うことは容易です。しかし、根拠に基づいた客観的判断などを自立して行うことは難しいと思われます。様々なことを自動化しても、個別性や専門性を求めると、まだまだ人の力が必要だと考えます。その人の力は保険下でないと届きにくいのが現状です。技術の進化と並行してサービスを提供できる環境の多様化が必要と考え、自費リハビリが存在します。これまであった支援サービスを使い尽くした最終手段ではなく、介護予防や生活支援を考えた時、何が「効果的か」を軸に考えることで介護予防が実現するのではないでしょうか。
※ICT:Information and Communication Technologyの略。 情報(information)や通信(communication)に関する技術の総称。
※AI:AI(Artificial Intelligence)とは人工知能の略で、コンピューターが人間の知的な行動を再現する技術。